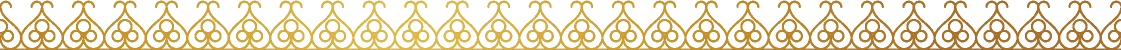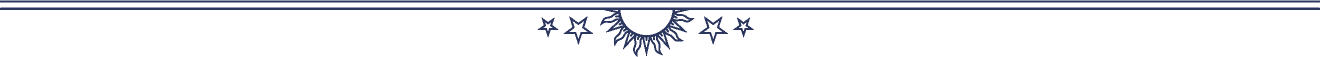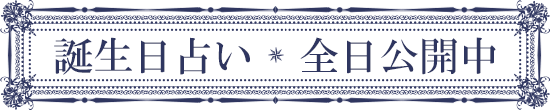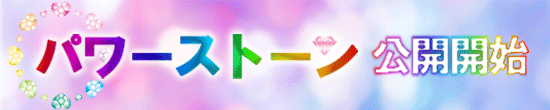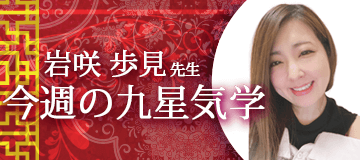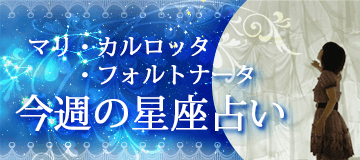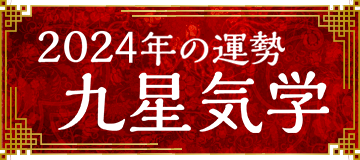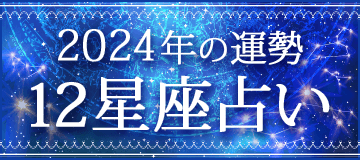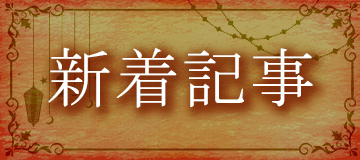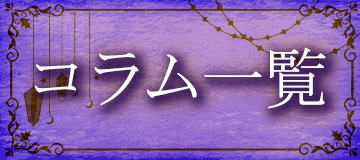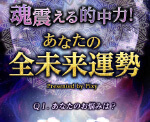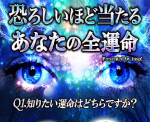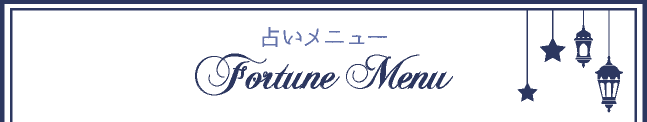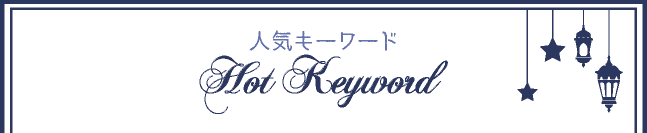大アルカナと小アルカナ、タロットカードを構成する2グループの違い
≪初心者必見≫タロットカードにおける大アルカナと小アルカナの違い


中世をイメージさせる絵が特徴的なタロットカードの起源は古く、13世紀ごろに遊戯用カードとして用いられていたようです。
カード1セットのことを「デッキ」といい、タロットカードは78枚で構成されています。
そのうちの22枚が「大アルカナ」、56枚が「小アルカナ」
と、2つのグループに分類されます。
大アルカナはタロットカードの主要な要素となり、0番から21番までの番号と「愚者」や「正義」などの固有の名前を持ちます。
小アルカナはトランプと似た構造になっており、四大元素である「火・地・風・水」を表す「棒」「金貨」「剣」「聖杯」の4つのスートに分類され、それぞれ1から10までの「数札」と、4枚の人物が描かれた「コード(宮廷)カード」の全14枚が1セットになっています。
なお、タロット占いでは大アルカナだけ使用するものや、小アルカナも含めて使用する場合などさまざまです。

タロットカードについて知識のない人は、そもそも「アルカナ」がどういった意味であるかを知らないかと思いますが、
アルカナとは、「机の引き出し」を意味するラテン語「arcanum(アルカーヌム)」の複数形「arcana(アルカナ)」が由来。
机の引き出しという意味から、引き出しに「隠されたもの」を指し、さらにそれが転じて19世紀頃からは「秘密」「神秘」などの意味として使われるようになったとされています。
では、タロットカードにおける「大アルカナ」と「小アルカナ」は一体何が違うのかといいますと、
カードが示すテーマが異なるのです。
大アルカナは「精神の成長過程」のストーリーと捉えると分かりやすいかと思いますが、0番のスタートの前段階「愚者」からはじまり、1番の動き出す準備が整った「魔術師」、2番のヒントを与える「女教皇」というように、最後の21番「世界」へと向かって成長していきます。
内面の変化や成長を表して、特定のエネルギーやメッセージを伝えるので、重要な決断や人生の目的や意味を理解するために使用するとよいでしょう。
そして、小アルカナは魂の成長ストーリーの中で出会う、日々の出来事や体験、感情を描いたカードとなり、基本的には日常生活の中で短期的に解決できることを意味しています。
カードの絵柄は、大アルカナのような神や死神が登場するものとは異なり、現実に存在するような人物や情景が描かれているのが特徴的。
「大アルカナ」と「小アルカナ」の違いを簡単にまとめると、
大アルカナは「象徴的なテーマ」
小アルカナは「具体的な出来事や登場人物」
と覚えておきましょう。
今の状況を大まかに示してくれる大アルカナ、それを詳しく掘り起こしてくれる小アルカナ、といったようにイメージするとリーディングしやすくなりますよ。

さて、実際に占う場合には冒頭でお伝えしたように、大アルカナ22枚だけ使用するものや、小アルカナも含めた全78枚を使用する場合など、その方法は実にさまざまです。
象徴的なテーマを示してくれる大アルカナは大きな視点から見た本質のため、過去・現在・未来といった時系列の成長過程や、現状の悩みがどのようにして変化していくかを確認するのに役立ちます。
- 人生の方向性や目的
- 重要な決断や課題
- 人間関係やパートナーシップ
などの内容を占うのに最適でしょう。
このような大きな問題や長期的スパンで知りたいのであれば、大アルカナを使った方法で占ってみましょう。
一方、小アルカナは、日常の細かな出来事や短期的な悩みを占う際に便利です。
小アルカナの絵柄には象徴するアイテムと数字が描かれているため分かりやすいでしょう。
- 日常の課題や問題
- 日常の選択や決断
- 感情や心の状態
- 人間関係や恋愛
など、小アルカナのカードは多岐にわたるテーマに対応しています。
自分が関心を持っている内容や課題に関連した質問を占ってみると、より具体的なアドバイスを得ることができるかもしれません。
なお、大アルカナと小アルカナのすべてのカードを使用して占う場合には、様々なテーマや状況に対応することができます。
- 人生における総合的な助言
- 特定の人との関係の状態や進展、アドバイス
- 困難や課題に対する解決策やアドバイス
- 自己啓発や自己実現に向けた方向性についてのアドバイス
など、大アルカナと小アルカナを組み合わせて占うことで、より深い洞察とアドバイスを得ることができます。
タロット占いの際には、自分の関心やニーズに合わせてカードの意味を解釈し、直感とつながりながら解釈していくことが重要です。